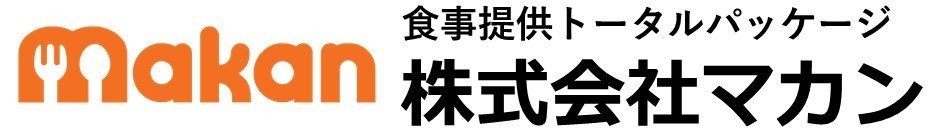【食と暮らしのコラム 第4話】
はじめに:「冬のだるさは、血糖のゆらぎが関係しているかも」
寒くなると、朝から体が重い、午後に眠くなる、夕方になると急に疲れる
そんな経験はありませんか?
それは単なる「寒さのせい」ではなく、血糖値の変動が関係していることがあります。
食事のあと、血糖値が急に上がり、その後に急降下すると、倦怠感や眠気、イライラが起こることがあります。
これは「血糖値スパイク」と呼ばれる現象で、体のエネルギーがジェットコースターのように上下する状態です。
体は急な変化に弱い生きもの。
血糖値の波をなだらかに保つことが、冬の疲れをためないコツです。

目次
血糖値の波と「疲れ」の関係
これが安定していると体も心もスムーズに働きます。
一方、血糖値が乱れると、集中力の低下や気分の不安定、慢性的な疲労につながることがあります。
血糖値が急に下がると、体は「エネルギー不足」と判断し、アドレナリンを分泌してブドウ糖を補おうとします。
その結果、動悸がしたり、甘いものを欲したり。
これが午後の「甘いもの欲求」の正体である場合もあります。
また、血糖値の変動が続くと、一時的に血流調整が乱れ、冷えを感じやすくなることもあります(個人差あり)。
『冬の疲れ』の正体は、血糖の波にあることも。
食べ方を少し変えるだけで、体の調子が穏やかに整うことがあります。
なだらかな血糖コントロールのための3つの食べ方
① 「主食・主菜・副菜」をそろえる
② 「食べる順番」を意識する
③ 「温かい汁物」で代謝とリズムをサポート
栄養士の視点:血糖値の安定は「心の安定」にもつながる
食事・体温・睡眠のリズムをそろえる
栄養士のメッセージ
まとめ
• 冬のだるさや倦怠感には血糖の変動が関係している場合がある
• 「野菜→主菜→主食」の順で食べると血糖値スパイクを防ぎやすい
• 温かい汁物は消化を助け、満腹感を高め、食事リズムを整える
• 血糖の安定は心の落ち着きにもつながる
• 食事・体温・睡眠のリズムを整えることで、冬の疲れを翌日に残さない
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回は疲労時に意識したいミネラル~鉄・亜鉛・マグネシウムのバランス~をご紹介いたします。
どうぞお楽しみに。
参考文献:
- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準」
- 厚生労働省 「e-ヘルスネット 栄養・食生活」
【免責事項】
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、
個別の医療アドバイスや診断を目的としたものではありません。
お身体の状態はそれぞれ異なります。
持病をお持ちの方や食事制限が必要な方、また気になる点がある場合は、
安全のため、必ず主治医(かかりつけ医)にご相談ください。