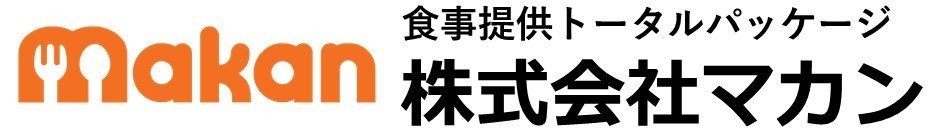【食と暮らしのコラム 第3話】
はじめに:「免疫は『腸』からはじまる」
冬になると、風邪や感染症だけでなく、なんとなく気分が沈んだり、疲れが抜けなかったりする日が増えます。
その原因のひとつが、「腸のコンディション」です。
実は、免疫細胞の多くは腸に存在しています。
腸は単なる「消化器官」ではなく、体の防衛を担う大切な拠点。
さらに、脳と神経ネットワークで密接につながっており、心の状態にも深く関わっています。
健康を保つには、まず腸内環境を整えること。
体調も気分も、「おなかの状態」に左右されやすいのです。
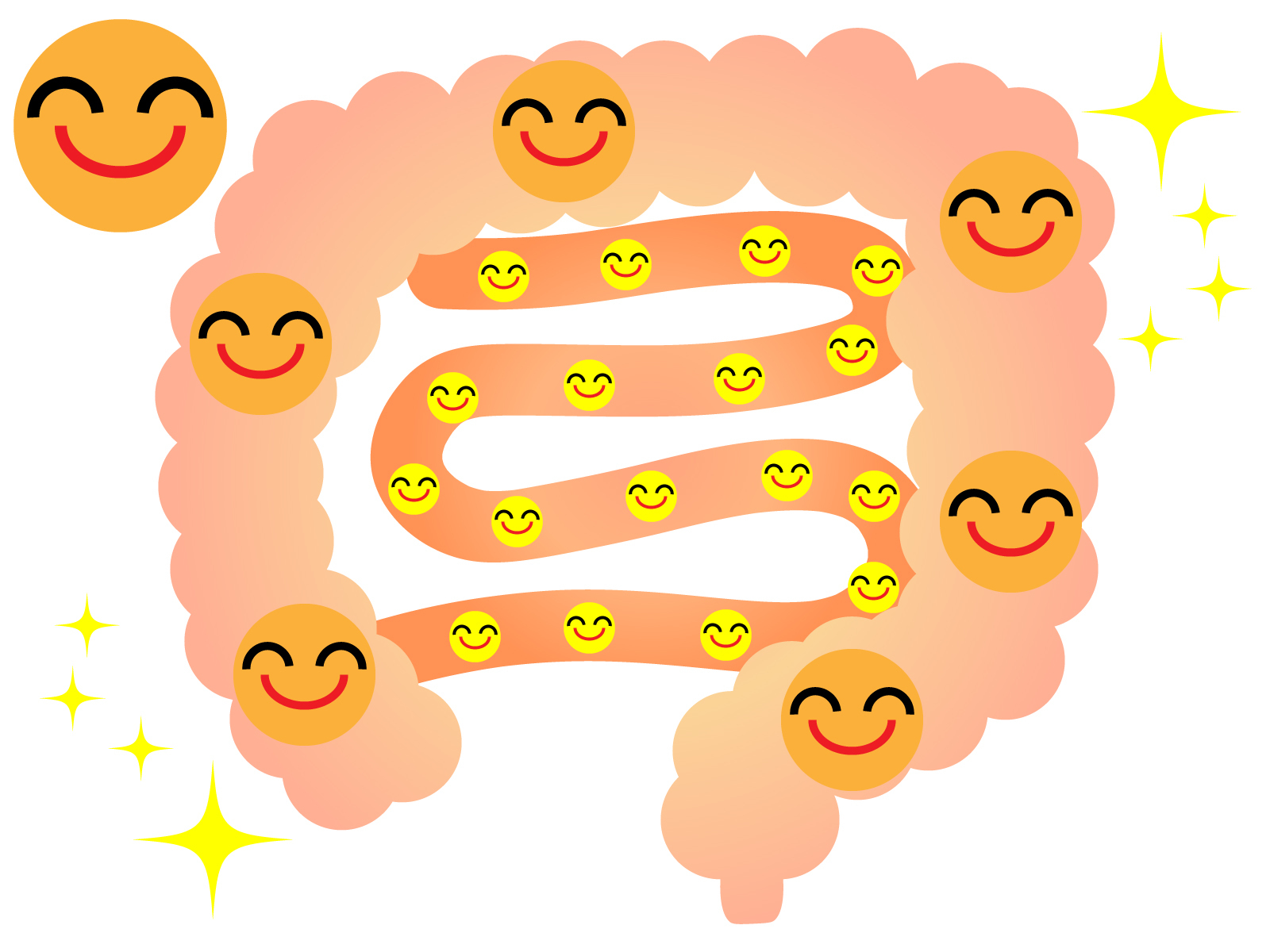
目次
『第二の脳』が教えてくれる、心と腸のつながり
腸内環境と免疫の深い関係
これらの細菌たちは、善玉菌・悪玉菌・日和見菌という3つのグループに分かれ、
小さな社会のようにバランスを取り合いながら暮らしています。
善玉菌が多い状態では、腸の粘膜が整い、免疫細胞がスムーズに働きやすくなります。
反対に、悪玉菌が優位になって腸内環境が乱れると、
腸の中で炎症が起こりやすくなり、免疫機能が低下することもあります。
その結果、風邪をひきやすくなるだけでなく、
肌の調子、便通、気分の浮き沈みなど、さまざまな不調となってあらわれます。
腸は、免疫の『訓練場』。
毎日入ってくる食べ物や細菌に反応しながら、防御の仕組みを育てています。
① 発酵食品で「善玉菌をとり入れる」
② 食物繊維で「善玉菌を育てる」
③ 腸を休ませて「リズムを整える」
食べ過ぎや遅い時間の食事が続くと、腸は休むタイミングを失ってしまいます。
夜は本来、腸が自分自身を修復し、働きを整えるための時間です。
消化をスムーズにし、翌朝のすっきりした感覚を得るには、
就寝の2〜3時間前までに食事を終えるのが目安です。
ただし、年齢・体調・持病・服薬の内容によって最適なタイミングは人それぞれ。
とくに糖尿病など治療中の方は、
かかりつけ医など医療専門家の指導を優先することが大切です。
そのうえで、自分の体調や専門家の助言に合わせて「無理のない・心地よい間隔」を見つけていくことが、腸を整える第一歩になります。
腸の調子を観察することは、自分の暮らしのリズムを観察することでもあります。
「昨日より少し楽」「今日はお腹が軽い」―そんな感覚を大切に、
少しずつ自分に合ったリズムを育てていきましょう。
冬の腸を守る食べ方の工夫
栄養士の視点:「腸を整えるとは、暮らしを整えること」
まとめ
• 「菌をとり入れる」「菌を育てる」「腸を休ませる」が腸ケアの三原則
• 腸と脳は神経でつながり、心の状態にも影響する
• 温かい食事・よく噛む・規則正しい食事時間が腸のリズムを整える
参考文献:
・厚生労働省「日本人の食事摂取基準」
・厚生労働省 e-ヘルスネット「食物繊維の必要性と健康」
【免責事項】
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、
個別の医療アドバイスや診断を目的としたものではありません。
お身体の状態はそれぞれ異なります。
持病をお持ちの方や食事制限が必要な方、また気になる点がある場合は、
安全のため、必ず主治医(かかりつけ医)にご相談ください。