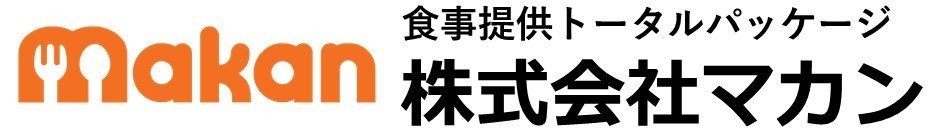【食と暮らしのコラム 第2話】
はじめに:「冷えた体では、免疫は働けない」
冬の風が冷たくなるころ、朝の体温が下がり、なんとなく動きが鈍く感じる日が増えてきます。
この「冷え」は、単なる不快感ではなく、体を守る免疫の働きにも関係しています。
体温が下がると血流が滞り、免疫細胞の動きが鈍くなるといわれています。
つまり、体が冷えると免疫の『指揮系統』もゆるやかになってしまうのです。
免疫は温度と代謝に正直。だからこそ、冷えは冬の健康管理の大きなテーマになります。
では、どうすれば体の内側から温め、免疫を支えられるのでしょうか。
答えは、特別な食材ではなく、日々の台所の積み重ねの中にあります。
たんぱく質と温性食材―この2つの組み合わせが、冬を乗り越える心強い味方です。

目次
たんぱく質:免疫の設計図を形にする「職人」
これらの多くは、すべて『たんぱく質』から作られています。
たんぱく質は、免疫の設計図を実際に形にする職人のような存在です。
材料が不足すれば、どんなに優れた設計図があっても完成しません。
風邪をひきやすい、疲れが抜けない、肌荒れが続く
そんなサインは、体が「素材不足」に陥っている合図かもしれません。
たんぱく質が十分にあることで、体は新しい細胞を作り替え、傷ついた部分を修復し、免疫を支える仕組みを整えていきます。
また、たんぱく質は「体を温めるエネルギー源」でもあります。
食後に体が自然と温まるのは、「食事誘発性熱産生(DIT)」と呼ばれる生理的反応です。
特にたんぱく質を含む食事はこの働きが強く、体の中に小さな暖房を灯すような効果があります。
しっかりとたんぱく質を摂ることは、体の防御力を静かに支えることでもあるのです。
温性食材:血流を促し、栄養を届ける「サポーター」
たんぱく質が職人なら、温性食材は血流を促し、栄養を届ける『サポーター』です。
生姜、ねぎ、にんにく、ごぼう、にんじん、味噌、発酵食品、これらは古くから冬の台所に欠かせない存在です。
単なる『体を温める食材』というより、血流と代謝のめぐりを整える知恵が詰まっています。
たとえば、生姜に含まれるショウガオールは、加熱によって生まれる成分で、血行を促し体の表面を温めます。
にんにくやねぎの香り成分であるアリシンは、血管を広げ、冷えやすい手足まで酸素や栄養を届ける手助けをします。
味噌や納豆などの発酵食品には腸内環境を整える力があり、腸の働きを通じて免疫を支えるとされています。
こうした『体のめぐり』を整えることは、単に寒さをしのぐだけでなく、「免疫細胞が働きやすい環境を整えること」につながります。
温性食材は、まさに科学と伝統が重なり合う暮らしの知恵なのです。
栄養士が考える「チームプレーの献立哲学」
体を支える栄養素は、どれか一つで完結するものではありません。
たんぱく質の代謝を助けるのはビタミンB群であり、その働きを安定させるのはミネラル。
さらに脂質は、ビタミンAやEといった脂溶性栄養素の吸収を助け、粘膜や細胞膜の健康維持に関わります。
このように栄養素は互いに支え合いながら、体のバランスを保っています。
献立を考えるときに大切なのは、特別な食品を選ぶことよりも、それぞれの料理が役割を補い合うように意識することです。
主菜ではたんぱく質を、副菜ではビタミンや食物繊維を、汁物では水分やミネラルを、といった具合に、
食材どうしの『つながり』を考えることで、自然と食事全体の調和がとれます。
温かさや香り、食感を大切にすることは、食事の満足感を高め、
結果として、心と体のリズムを穏やかに保つ助けになります。
食事づくりは、完璧を目指すことではなく、
「今日の一食が、明日の元気につながる」と考える小さな積み重ねなのです。
料理は科学であり、音楽のようでもあります。
素材ひとつひとつが異なる『音色』を持ち、それらが響き合うことで、食卓に調和が生まれます。
栄養士はそのハーモニーを整える伴奏者として、体と暮らしを心地よく支える存在です。
「温める」と「焦らない」の関係
冬の台所は、体を整える場所
まとめ
• たんぱく質は免疫を形づくる「職人」
• 温性食材は血流を促し、栄養を届ける「サポーター」
• 栄養は連携して働き、チームで体を支える
• 「温める」とは焦らず体を育てる時間
参考文献:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」
【免責事項】
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、
個別の医療アドバイスや診断を目的としたものではありません。
お身体の状態はそれぞれ異なります。
持病をお持ちの方や食事制限が必要な方、また気になる点がある場合は、
安全のため、必ず主治医(かかりつけ医)にご相談ください。