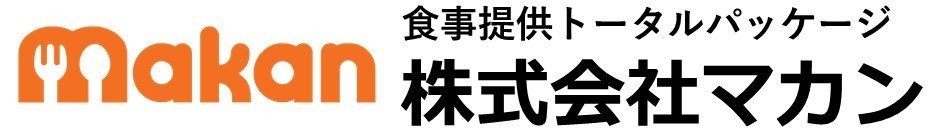【はじめての厨房-2】
一人ひとりの意識が、厨房全体の安全をつくる
冬が近づくと、厨房における衛生管理で特に注意すべき存在がノロウイルスです。
一度でも発生すると、わずかなウイルス量でも感染が広がりやすく、
施設全体の信頼を揺るがす大きな問題につながります。
その主な感染経路として注意すべきは、「人の手」と「二枚貝」です。
ノロウイルスは、二枚貝の体内にウイルスが蓄積されることがあり、
加熱が不十分なまま食べると感染するおそれがあります。
そのため、中心部まで85〜90℃で90秒以上の加熱を行うことが推奨されています。
この条件は、ノロウイルスの不活化に有効とされる方法の一つです。
調理の際は、中心部までしっかりと火を通すことで、感染リスクを大きく減らすことができます。
また、感染者の手指に付着したウイルスが、調理器具や食材、配膳台などを介して
他の食品に移ることで、二次的に感染が広がるケースも多く見られます。
つまり、感染経路は大きく「食材を通じた感染」と「人を介した二次汚染」に分かれます。
そして厨房の現場では、特に後者『人の手』を介した汚染が最も注意すべきポイントです。
たとえば、手洗いが十分でなかったり、体調の変化に気づかないまま作業を続けてしまったり。
そんな日常の中の「ちょっとした油断」が、思わぬ感染のきっかけになります。
また、厨房に入る方は、生の二枚貝の摂取を控えることで、
自覚のないままウイルスを持ち込むリスクを減らすことができます。
特に、不顕性感染(症状が出ない感染)の状態で業務に就くことを防ぐうえでも重要です。
つまり、ノロウイルス対策の基本は、
薬剤などの衛生管理手段を適切に使いつつも
何より大切なのは、厨房で働く一人ひとりの『個人衛生の徹底』です。
手洗い、健康チェック、服装管理。
この3つを丁寧に積み重ねることこそ、
厨房の安全と利用者の安心を支える、最も確実でシンプルな方法です。
目次
1. 感染のほとんどは『人の手』から
ノロウイルスは非常に小さく、わずか10〜100個程度でも感染が成立すると言われています。
他の食中毒菌が数千〜数万個必要なのに比べ、圧倒的に少ない量で感染が成立するため、極めて感染力が強いのが特徴です。
調理や配膳に関わる人の手指にウイルスが付着すると、まな板、包丁、食器、配膳台などを通じて食品に移り、施設全体へと広がってしまうことがあります。
特に注意が必要なのは、自覚症状が出る前の「潜伏期間中」でも感染力を持つという点です。
「自分は大丈夫」と思って作業を続けてしまうと、気づかぬうちにウイルスを広げてしまうおそれがあります。
厨房の清潔さは、設備の整備だけでなく、一人ひとりの手の衛生意識から始まります。
「自分の手が、厨房全体の安全を支えている」
その意識こそが、感染を防ぐための第一歩です。
2. 個人衛生の3つの柱
①手洗い:「すべての衛生の出発点」
厨房での手洗いは、単なる「決まりごと」ではなく、すべての衛生管理の出発点です。
トイレを使用した後、食材を扱う前、生の肉や魚を触ったあと、
ゴミ処理や清掃をしたあと、盛付けや配膳に移る前、
そして調理を終えたあと等にその都度、手洗いを行うことが大切です。
1回の手洗いはほんの数分ですが、
その一手間を惜しむだけで、数十人分の食事を汚染してしまうおそれがあります。
手洗いは、安心と安全を守るいちばん身近な「予防策」。
厨房で働くすべての人が、日々の習慣として丁寧に行うことが、
感染を防ぐ最も確実な方法です。
正しい手洗いの手順(5ステップ)については関連記事:
『手洗いに始まり、手洗いに終わる』で詳しく紹介しています。
②健康チェック:「体調の変化を見逃さない」
➂服装と身だしなみ:「清潔をまとう」
3. 感染を防ぐ『厨房の空気』をつくる
まとめ
ノロウイルスの感染を防ぐためには、薬剤や設備などの対策ももちろん重要ですが、
その土台となるのは、一人ひとりの衛生意識と日々の習慣です。
手洗い・健康管理・服装の清潔。
この3つが確実に守られてこそ、厨房の安全と利用者の安心が生まれます。
そして、最も大切なのは「当たり前を続けること」。
一日一日の積み重ねが、利用者の健康、職員の安全、そして施設全体の信頼を守ります。
一人ひとりの意識が、「感染を防ぐ力」になる。
それが、真に安心できる厨房づくりの第一歩です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
次回は、検便が守る『見えない衛生管理』をご紹介いたします。
どうぞお楽しみに。
出典:
• 厚生労働省『大量調理施設衛生管理マニュアル』
• 厚生労働省『ノロウイルスに関する Q&A』