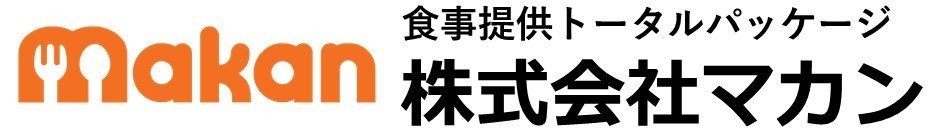高齢者施設の厨房はいま、大きな転換期を迎えています。
人手不足、スタッフの高齢化、そして働き方改革による労働時間の制限。
「昔ながらの手作り」を続けたくても、現場の体制がそれを支えきれなくなっている施設も少なくありません。
「どうすれば、安全で温かい食事を無理なく提供できるのか?」
そんな問いを抱える現場の声に耳を傾けると、そこには『作る人を守る仕組み』を求める切実な思いが見えてきます。
現場が抱える課題
① 人手不足とシフトの限界
調理員の確保が難しく、限られた人員で毎日の食事を作り続ける現実があります。
「早朝出勤や休日対応が当たり前になっている」
「一人休むと全体のスケジュールが崩れる」
といった声は、多くの施設で聞かれます。
特に高齢者施設では、朝食・昼食・夕食の提供時間が決められたタイムスケジュールなので、少しの遅れがサービス全体に影響します。
ベテラン職員に頼る体制が続くことで、若手の育成や引き継ぎの時間が取れないという悪循環も生まれています。
こうした状況を抜け出すには、「個人の努力」ではなく「仕組み」で厨房を支える」発想が求められています。
『属人化しない調理体制』をどう築くか──それが、これからの厨房運営の鍵です。
② 調理時間と作業負担の増大
仕込み・加熱・盛付け・配膳といった厨房業務は、常に時間との戦いです。
食事提供作業ピーク時には、ほんのわずかな手違いでも提供が遅れてしまうことがあります。
特に仕込みや調理には、経験や勘に頼る場面も多く、スタッフ間で作業量や仕上がりに差が出るのも現場の悩みです。
また、「温かいものは温かいうちに」「冷たいものは冷たく」提供するための温度管理と品質管理にも、細やかな注意が必要です。
それが日々のストレスや疲労の蓄積につながり、結果として人員の離職や体制の不安定化を招いてしまうケースも少なくありません。
「限られた人員で、同じ品質を保つ」
この課題を解決するには、作業工程そのものを見直し、時間と労力をかけずに品質を維持できる体制づくりが不可欠です。

『省力化』という考え方
ここ数年、厨房運営を見直す動きが各地で広がっています。
単に作業を減らすことが目的ではなく、
「限られた時間と人員の中で、より安全で美味しい食事を届ける」という視点から、
『省力化』という考え方が注目されています。
その一つの答えが、献立形式の調理済み冷凍食品『マカン』を活用した仕組みです。
『マカン』調理済み冷凍食品は、仕込みや味付けをあらかじめ済ませてあるため、現場では再加熱や盛り付けなどの最終工程に集中できます。
火加減や味のばらつきを防ぎながら、調理時間を短縮できる点が大きなメリットです。
実際に導入した施設では、次のような変化が見られています。
☺「慌ただしさが減って、落ち着いて作業できるようになった」
☺「スタッフの入れ替え時も、作業の引き継ぎがスムーズになった」
こうした『時間のゆとり』は、単なる効率化ではなく、
現場の負担を減らし、スタッフ同士の連携を深めるきっかけにもなっています。
すなわち人と人、仕事と環境の“調和”を取り戻すプロセスでもあります。
省力化とは、単に作業を減らすことではなく、
人の感性やつながりを活かすための余白を生み出すこと。
つまり「人にしかできない仕事」を取り戻す手段なのです。

まとめ
厨房の課題は「人」や「設備」だけの問題ではありません。
それは、『働く環境をどう整えるか』という経営のテーマでもあります。
調理の効率化を考えることは、
食の質を守ること、そして働く人の笑顔を守ることにつながります。
現場で働く一人ひとりが、
「無理なく、いい食事を届けられる」
そんな日常をつくるために。
マカンは、これからも現場とともに考え続け、
『人を支える厨房の仕組みづくり』を追求していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
次回もお楽しみに!!!